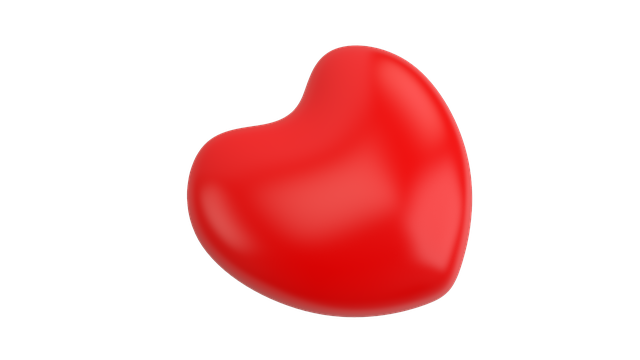東洋医学の基本概念の1つに『気血水論』というものがあります。
前回は『気』についてお話をしましたので、今回は『血』についてお話をしていきます。
東洋医学独特の概念は、現代医学と合致している部分もあったりします(歴史的には、東洋医学の方が深いんですけど笑)。
ここでいう『血』は、臓器同様に現代医学とはちょっと異なるものです。なので、「東洋医学では、そんな感じなんだ~~!」というフラットな気持ちでお読みしていただくと頭にスッと入るかと思います。
科学がすべてではないとは思っていますし、東洋医学の中で科学的根拠がでてきているものを順次お伝えしていきます。どうぞ楽しみにしてください<m(__)m>
≪Contents≫
各器官の栄養とメンタルの基礎となる物質
『気・血・水』の『血』は、基本的に血液のことを指しますが、栄養分全体も表しています。
『血』は飲食物から得られる水穀の精微(栄養分)と大気から作られた「宗気」が「営気」と「衛気」に分かれ、さらにそのうちの営気が『血』に転化されることで作られます。
これは、体内の各器官に栄養分を供給し、滋養する働きをするので『営血』とも呼ばれています。
『血』は『気』とのかかわりが深く、『気』の作用によって『血』の働きが支えられているともとれます。
『気』の作用によって『血』が体外に漏れることなく、体中をめぐっているのです。
『血』の働き
東洋医学には『陰陽論』というものがあり、『気』が『陽』であるのに対し、『血』は『陰』に分類されます。
『血』の働きには、次のことがあります。
- 身体の各器官、組織に栄養分を与え、うるおす。
- 『気』とともに人間が精神活動をおこなう基礎となる物質であり、意識や精神を明瞭にする働きがある。
『血』に関わる臓器
『血』の生成に関わる臓器には、次のようなものがあります。
- 肺:『血』のもととなる新しい大気を取り入れ、宗気を作りだす。
- 脾:『血』のもととなる水穀の精微を供給する。また、血液が脈管の外に漏れないように運行を管理する。
- 心:ポンプ作用により、全身に栄養分を運搬するとともに、血液を統括する。
- 肝:血液を貯蔵するとともに、全身の栄養分布(量の調整)や血の解毒をつかさどる。
ここで出てくる臓器は、いわゆる“西洋医学(現代医学)”とはニュアンスが異なるものです。
似た作用を持っているということはありますが、西洋医学のような解剖学的具体的臓器ではないので、基本的には別物として認識してください。
『血』の変調
東洋医学の『血』は、西洋医学における血液のことだけを意味しているわけではありません。
『気』とともに精神活動の基礎となる物質と考えられていて、血の状態によって、私たちの心身の状態が大いに変わってくるのです。
身体の不調が慢性化して『血』に影響が及ぶと、活性が失って正常な働きができなくなります。
そのため、貧血を起こしたり、自律神経の働きや女性ホルモンのバランスなどが崩れたりします。
『血』の変調は、特に女性は注意が必要です。
女性特有の婦人科系のことで『血』が不足になりやすく、体調不良に陥りやすいです。
特に現代は、PMS(月経前症候群)になりやすい環境にあります。
いままで診てきた中でも、
- 栄養の偏りのある食事
- 体を冷やしやすい服装
- ストレスのかかりやすい生活・環境
etc…
これらの影響で、血行が悪くなりやすい、血量が不足しやすい状態になりやすいのです。
もちろんこれらがすべてではなのですが、現代人は生活習慣などによって『血』が不足しがちです。
『血』に関する変調には次のようなものがあり、各々によって症状が異なります。
血虚(けっきょ)
血量不足、血の機能が低下している状態です。
造血機能の低下や月経過多などの失血過剰、瘀血、脾胃の変調、栄養不足によって引き起こされます。
特に女性に多くみられます。
【主な症状】
- めまいや立ちくらみ
- 目がかすむ
- 動悸
- 貧血、全身の倦怠
- インポテンツ、不妊症
- 顔色や皮膚につやがなく、ガサガサしている
- 爪がもろい
- 寒がり
瘀血(おけつ)
血液や血流の障害(主に筋肉のコリや血液の状態が良くない等による血行不良)、婦人科系の代謝不全などで起きます。
気虚や気滞、飲食の不摂生、喫煙、飲酒過多などが原因で引き起こされます。
【主な症状】
- 皮膚の黒ずみ
- 冷えのぼせ(足元が冷えているのに頭がのぼせる)
- めまい
- 頭痛
- 肩こり
- 痔
- 月経不順
- あざができやすい
- 吹き出物
- 頭部や上半身に汗をかきやすい
- 月経痛や月経時のイライラ
出血(しゅっけつ)
様々な出血が起きている状態です。
瘀血が原因の場合や気虚が原因の場合、感染症や外傷が原因の場合があります。
【主な症状】
- 吐血
- 鼻血
- 下血
- 痔出血
- 月経過多
- 腸内出血
- 不正出血
- 貧血
- 血が止まりにくい
- 手術や出血が多いけがの後
『血』を良好に保つ方法
『気』『血』『水』のバランスによって、身体は成り立っております。
病気になってしまうときは、この3つのバランスが崩れて循環が滞ったり、不足したりして、内臓などがうまく機能しなくなることでおこります。
この3つは、どれかが単独で変調を起こすというよりかは、複合して起こることが多くあります。
基本的には、以下の3つをおこなうと良いでしょう。
- 空気を清潔に保つ
- 多食・偏食せずに食事をする
- 水分補給を意識しておこなう
このことは『気』のブログでもお話をしましたが、それだけ単純で重要なことなのです…。
現代社会を生き抜くためにも、自己管理や鍼灸施術をとおして、心身の状態を万全にしておくことが大切です。
特に『血』を良好に保つ方法は、以下のようなことがあります。
- 無理をせずに、自分のペースで生活する
- 栄養のある食事、良質の肉や豆類からタンパク質を摂取する。
- 体を冷やさない(特に足首を冷やさないようにする)。
- あまいものやからいもの、刺激の強いものを摂取しすぎない。
『血』は、僕らの体に栄養を与え、メンタルを良好に保つ物質です。
『血』を満ちあふれさせることで、僕らは心身ともに“イキイキ”活動できます。
ですが、現代人は、生活習慣の乱れや不摂生などによって『血』が不足したり、上手く巡っていなかったりします。
単純なことではありますが、『血』のためにも『運動をする』ことです。
運動をすることで筋肉を刺激し、血行を良好にすることができます。また、運動をすることによって『気』も巡りますので、メンタルも良好になります。メンタルに良いことは科学的根拠もありますので、東洋医学的にも合致している部分です。
もし自身で心身を整えることが難しい・助力が必要でしたら、どうぞ僕の鍼灸施術をご活用ください☆